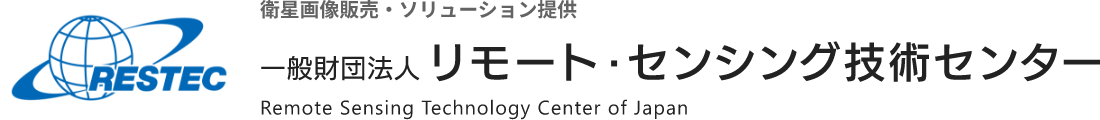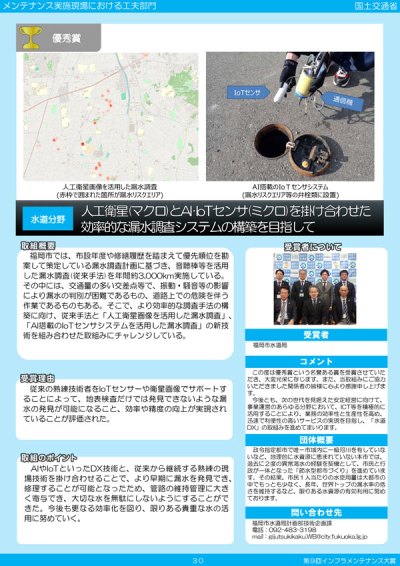一滴の水も無駄にはしない。 世界トップレベルの低い漏水率を維持 -最先端の漏水調査手法の構築に衛星データも活用-
福岡県福岡市では、人工衛星を活用した漏水調査の実証が進められてきました。漏水率では世界トップレベルの低い水準を維持されています。
福岡市の先端技術公共調達サポート事業の公共調達第一号として、RESTECが選定された人工衛星を活用した漏水調査について、福岡市水道局 福永晋也技術調査係長にお話を伺いました。
福岡市水道局全体の役割について教えてください。
- 福岡市民約165万人の方々に安全で良質な水を安定して供給する事が第一の使命です。市内の水道管は約4,100km張り巡らされています。その配水管を、いかに効率的なメンテナンスを行えるかが、今後の大きな課題でもあります。しっかりメンテナンスすることで、貴重で大切な水をさらに有効的に活用できるため、衛星リモートセンシング技術の活用を実証から順次進めています。
-

福岡市の低い漏水率は世界トップレベルと聞きます。世界トップレベルを維持するには、福岡市独自で厳しい漏水調査を実施されるのでしょうか。
諸外国に比べ日本全体の漏水率は低いですが、東京都をはじめ政令市と比較をしても、6~7年連続、特に福岡市が低い漏水率の値をキープしています。その事実から世界トップレベルと表現させてもらっています。
福岡市の地理的背景として、政令市の中で唯一、一級河川が地域内に流れていません。他の政令市では、一般的に水が豊富にあることが影響し、大きな河川が流れる場所が大都市化します。
福岡市の場合、福岡県南部に流れる一級河川の筑後川から水をいただいているため、せっかくいただいた水を一滴も無駄にはしないという思いがあります。また、福岡市は昭和53年と平成6年に、給水制限が発出されるような大規模な渇水を経験していますので、水に対する思いは強いと思います。昭和30年代頃から計画的に漏水調査を実施しています。先人達が築いてきた結果が今、漏水率の低さに繋がっているのかなという認識です。
「先端技術公共調達サポート」として「人工衛星画像を活用した水道管漏水調査」を選定した狙いを教えてください。
先端技術公共調達サポート事業は、福岡市が独自で構築している「mirai@(ミライアット)」というスキームです。福岡市の行政課題と先端技術等をマッチングさせます。これまでの課題として、企業等と実証実験を通じて非常に有効な結果を得られたとしても、当該実証実験を実施してきた企業等と必ずしも契約できるとは限らない事が挙げられます。行政としては、やはり公平性を担保する必要がありますので仕方がない部分もあります。しかし、今回のような人工衛星を活用した先端技術に関しては、実証実験で得た有効な結果を、そのままスピーディーに実装したいという狙いを実現するために、mirai@を採用することとしました。
他県でも人工衛星を活用した漏水調査の導入を検討されていると思いますが、導入検討中の自治体に向けたアドバイスがあれば伺いたいです。
-
正直に申し上げると、実証実験を行う前は、地下に潜る配水管のことが人工衛星で分かるというイメージができませんでした。しかし、RESTECの方々と、対話を重ねていく上で人工衛星から得られる情報を徐々に理解することができました。我々もいきなり新技術に舵を切るのではなく従来の調査技術を活かしつつ、新技術を導入し、調査業務の効率化を図りたいという思いがありました。福岡市議会からも、新技術への取組は精度向上のためにも積極的に進めるべきだとご理解をいただき、福岡市、RESTECとともに実証実験フェーズへ進みました。
導入に際して、リモートセンシング技術に関して素人で分からない部分も多々ありましたので、外部有識者として専門家の先生方にご意見をいただきました。そのご意見を踏まえて福岡市としての方針を決めることが出来ました。どこの市役所でも宇宙の専門家は居ないと思いますし、市の職員では耳慣れない表現もあると思うので、有識者の意見を踏まえて進めて行くことで効率的な進め方が出来るのではないかと思います。
-

人工衛星のデータは、福岡市の水道行政にどのように役立つのか。また、人工衛星を活用する事への期待等をお聞かせください。
水道管から地中に漏れる水量の比率を、漏水率として算出しますが、最新の福岡市の値では、2. 0%となっています。福岡市の調べでは世界で最も低い位置付けです。従来の漏水調査では、基本的に人による現地調査を実施してきました。人海戦術で歩き回りながら漏水の音を確認しますが、従来の漏水調査方法に加えて、人工衛星データを活用した新たな技術による方法を掛け合わせることで、より一層低い漏水率を目指していく形に繋げられないかなと期待しているところです。配水管を音の異常値で確認する調査も行ってはいますが、配水管は地下に設置されているので目視での確認は難しい部分もあります。人工衛星を活用したリモートセンシング技術で異常場所を可視化することで、漏水調査の効率化に繋がることに期待しています。